7-1 貸倒引当金の概要
貸倒引当金は、現在の経済状況を反映して、貸倒れのリスクに備えるために設定することが望ましいと思いますので、
みなさんも一度検討して見てください。
貸倒引当金制度の改正で大きな点は、債権償却特別勘定が貸倒引当金の繰入限度額とし、必要経費に算入されることとなり、
この方法を個別評価といいます。従来は、債権償却特別勘定繰入として、必要経費に算入されていました。
ここで、注意しておいてほしいことがひとつあります。従来の債権償却特別勘定は、青色申告者だけでなく白色申告者にも
適用がありました。このため、貸倒引当金の個別評価は、青色申告者だけに限らず、不動産所得・事業所得・
山林所得の事業的規模の者に適用されます。これに対して、従来の貸倒引当金を意味する一括評価の適用は、青色申告者に限定され、
事業所得のみに適用されます。
7-2 貸倒引当金の繰入限度額
所得税法の不動産所得・事業所得・山林所得の金額を計算する上で、必要経費に計上する金額は、次の金額の合計額となっています。
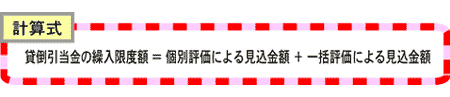
[1]個別評価(従来の債権償却特別勘定)
個別評価による貸倒引当金の繰入限度額は、従来の債権償却特別勘定の繰入額を意味しています。
事業の遂行上生じた売掛金・貸付金・前渡金等の金銭債権について、その年の12月31日におけるその全部または一部に損失が見込まれる、
次のような事由が生じた場合におけるそれぞれの金額が、個別評価による貸倒引当金繰入限度額となります。
ここでいう貸倒引当金の対象となる金銭債権は、資産損失の対象債権と同様です。
この個別評価による貸倒引当金繰入については、不動産所得・事業所得・山林所得の事業的規模の者に限られます。
| 長期棚上等 |
- 居住者の有する金銭債権(賃金等)について、次のような事実が生じた時は、その長期棚上げ、
または年賦償還されるもののうち、その事由が生じた年の翌年から5年後に返済または切り捨てられることとなった金額。
-
- 1.会社更生法等による更正計画許可の決定
- 2.和議法による和議または破産法による強制和議の許可の決定
- 3.商法の規定による特別清算に係る協定の許可または整理計画の決定
- 4.私的整理による合理的基準による債権者集会の協議決定等があったこと
|
| 認定基準 |
債務者が債務超過の状態が相当期間継続し、業務に好転の見通しがないことや
災害、経済事情の急変等により多大な損害が生じた等により、取立て等の見込
がないと認められる時におけるその金額に相当する金額。 |
| 形式基準 |
- 債務者について、次のようなこ事由が生じた場合における賃金等の額(実質的に債
権と見られない金額・
担保及び保証等により取り立ての見込まれる金額を除く)
-
- 1.会社更生法による更正計画許可の申立て
- 2.和議法による和議開始の申立てまたは破産法による破産の申立て
- 3.商法の規定による会社の整理開始または特別清算の開始の申立て
- 4.手形交換所による取引停止処分
|
※ この他に外国政府等に対する貸金等について、経済的価値が著しく減少し弁済を受けることが著しく困難な場合には、
その貸金等の額の50%相当額
[2]一括評価(従来の貸倒引当金)
一括評価による貸倒引当金の繰入限度額は、従来の貸倒引当金の繰入額を意味しています。
青色申告書を提出する本人が、事業所得を生ずべき事業の遂行上生じた売掛金・貸付金等の金銭債権について、その年の12月31日の金銭債権額を基礎として計算した次のような繰入限度額は、その事業所得の金額の計算上必要経費となります。
引当対象となる
金銭債権 |
個別評価と一括評価の対象となる金銭債権が重複することを避けるために、
個別評価の対象となった金銭債権は、一括評価による貸倒引当金の設定対象
とはしませんので、注意してください。 |
実質的に債権と
みられないもの |
この貸倒引当金の設定対象となる金銭債権は、同じ相手に債権と債務を有す
る場合のように実質的に債権とみられない金額を
控除した金額となります。
これには、個別法(原則)と簡便法の2つがあります。
- 1.個別法(原則)
- 個別法は、金銭債権の相手先ごとに個別に債権と債務を比較していずれか少ない金額を実質的に債権とみられない金額と
する方法です。
- 2.簡便法
- 個別に債権・債務を比較する作業は、相手先が多い場合など事務負担g大きくなりますので、
過去の実績に基づいた次の簡便法によることができます。
-
実質的に債権と
みられない金額 |
= |
その年の12月31日の金銭債権の額 |
× |
基準年度の12月31日における実質的に債権とみられない額の合計額 |
|
| 基準年度12月31日の金銭債権の合計額 |
|
※ ここでいう基準年度は、今年度の改正により平成10年度と平成11年度となりました。
ただし、平成11年度の確定申告までは、平成10年度、平成11年度の実質的に債権とみられない額がわかりませんので、
昭和55年度と昭和56年度が基準年度として計算します。ここで、平成10年度と11年度に実質的に債権とみられない額を簡便法で
行おうとする者は、昭和55年度より引き続き事業を営んでいなければなりませんので、注意してください。
| 繰入限度額の計算方法 |
繰入限度額は、次の計算方法により、その額を必要経費に計上します。
-
| 繰入限度額 |
= |
その年の12月3日の金銭債権合計額※ |
× |
5.5%(金融業は3.3%) |
|
※ 実質的に債権とみられない額と個別評価の対象となったものを除きます。
7-3 処理方法
今年 「貸倒引当金繰入額」として必要経費に算入。
翌年 「貸倒引当金戻入額」として収入金額になる。
7-4 その他の引当金・準備金
退職給与引当金等のように、青色申告者に限り引当金・準備金の規定により必要経費に算入されるものがあります。